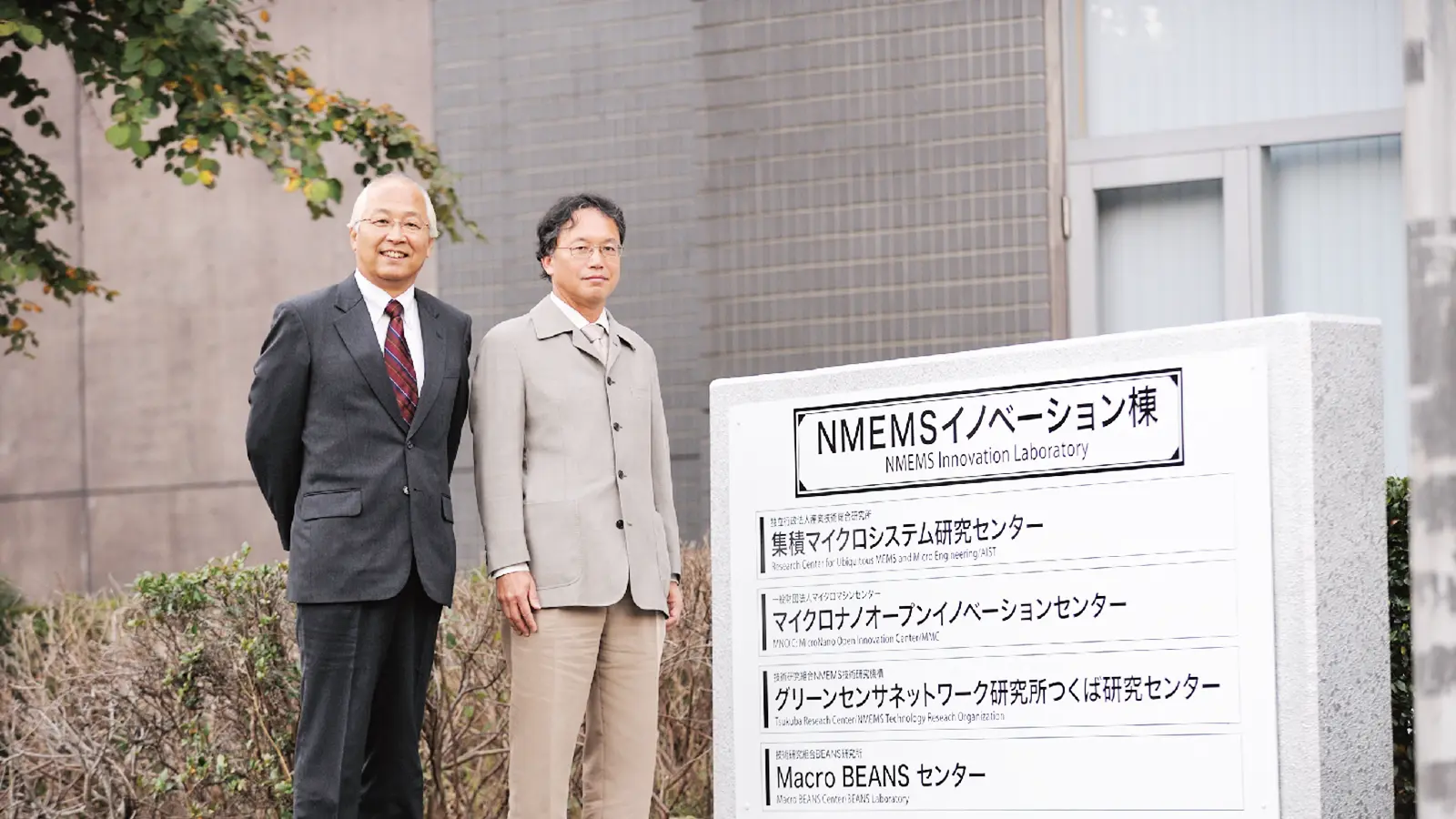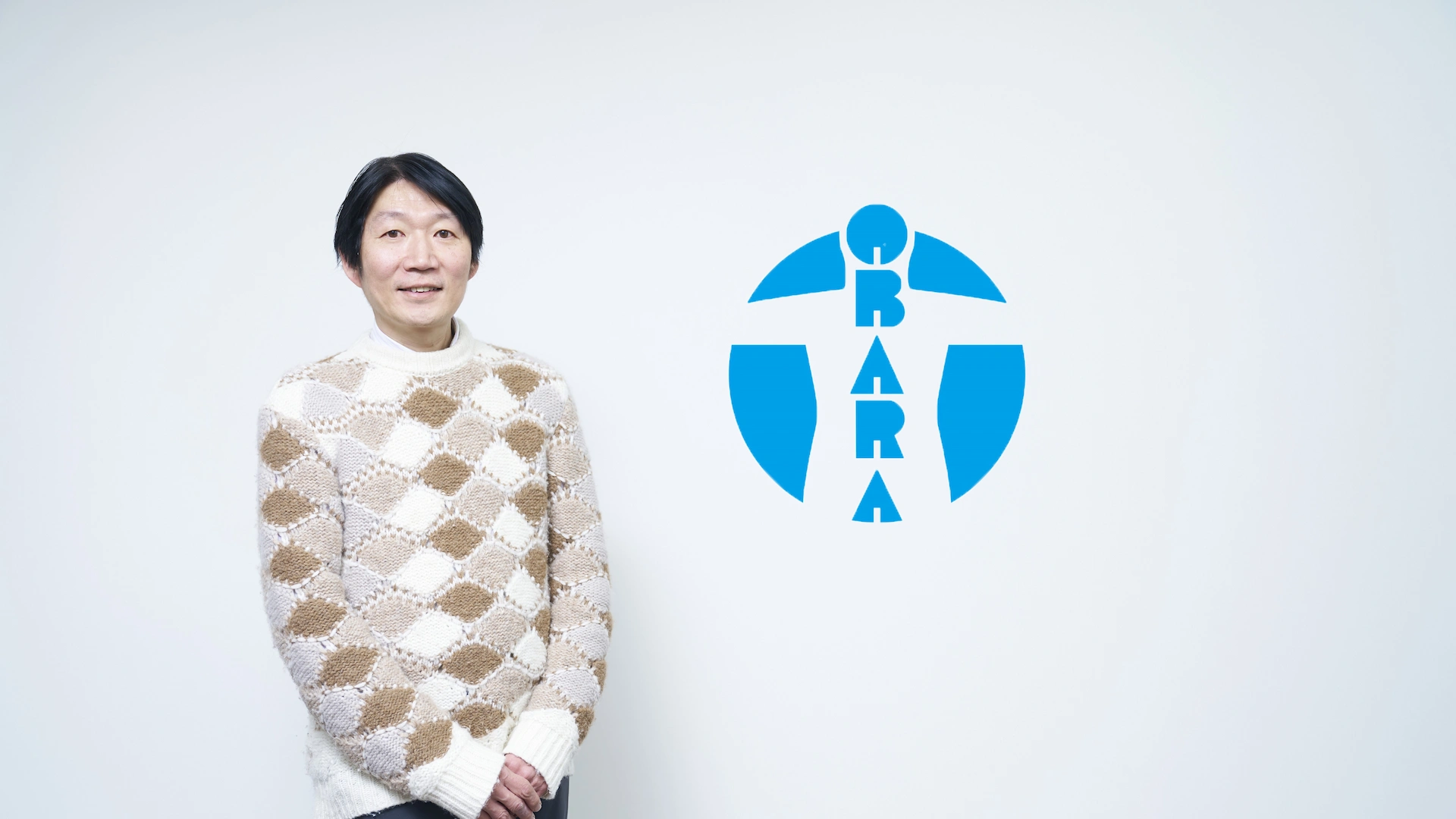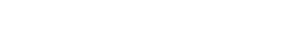芸術作品は、人類の長い歴史の中で数多く生み出され、今もさまざまなアーティストたちによって創造されている。
彫刻家の名和晃平氏。「今は表現が相対化されてしまって、作品をつくっても『これ、もう誰かがやっているよね』となってしまう。アーティストの中には閉塞感を感じている人も多いです」
コピー、焼き直し、既知感。アーティストは日々こうした悩みを抱え、そこから脱出する道を探っている。
名和氏は、留学先、大学院などで試行錯誤を重ねていくなかで、少しずつその壁を打ち破り、現代美術作家として地位を確立していく。

現代美術界の「時の人」
何台も設置されたテレビカメラ。当日、1,000人を超えたという人の群れ。名和氏があいさつをするべくマイクの前に立つと、名和氏を撮影しようと携帯電話を高くかかげ身を乗り出す人、人、人──。

『名和晃平──シンセシス』展。そのオープニングセレモニーが行われた東京都現代美術館は、異様ともいえる熱気に包まれた。名和氏は、「京都府美術工芸新鋭選抜展 最優秀賞」「京都府文化賞 奨励賞」「六本木クロッシング2007 特別賞」「第14回アジアン・アート・ビエンナーレ・バングラデシュ2010 最優秀賞」など数々の賞を受賞。フォークデュオ「ゆず」からオファーを受けて、CDジャケットのアートワークやコンサートステージ用の造形物も制作。今回の展覧会も、東京都現代美術館で男性作家として史上最年少での個展開催という快挙を成し遂げる。
まさに「時の人」なのである。
人気の秘密は名和氏が創り出す作品にある。高さが3mはあろうかという巨大な像の数々、壁面にへばりついた植物のツタを彷彿とさせる網状の造形、全身をガラスのビーズで覆われた剥製のシカ、小さな半透明の粒が透明の箱の中に整然と並べられ、見る角度によって異なる風景が立ち現れる造形物──。それらは一見なんの脈絡もないように思える。しかし一通り作品を見てみると、すべての作品に共通した雰囲気があるのに気づかされた。
「透明感、静謐感」。喜び、怒り、哀切、愛など、我々が常日ごろ抱えている「私情」を感じさせない無色透明な世界。それでいて見る者に、それまで覚えたことのないような奇妙な胸騒ぎ、感覚を覚えさせる不思議な作品群。
オープニングセレモニーで名和氏があいさつを終えると、割れんばかりの拍手が起こり、セレモニー終了後、名和氏はあっという間に多くの人に囲まれた。時代の先端を疾走する現代美術作家。だが15年ほど前には、名和氏は想像していなかったのだろう。「現代美術」の世界に身を置いている自分の姿を──。
ヨーロッパで起こった転換
名和氏は1975年大阪生まれ。京都市立芸術大学に入学するが、夢中になっていたのは、京都奈良にある神社仏閣巡り。仏像や神像ばかりを見て回っていた。「僕が興味をもっていたのは『宗教美術』でした。彫刻を選んだのも宗教美術の影響からです」現代美術にはさほど興味はなく、展覧会があっても足を運ぶことはなかったという。1998年、ロンドンにある英国王立美術院に留学。そのときには、神像を見て回るため、ヨーロッパ各地の教会巡りや、大英博物館、ルーブル美術館に足繁く通った。

ところがロンドンで暮らす中、名和氏は現代美術の世界で活躍するアーティストの作品を目にする。アントニー・ゴームリー、レイチェル・ホワイトリード、アニッシュ・カプーア──。ヨーロッパを代表する現代美術の騎手たちが創り出した彫刻を前にして、名和氏は気づかされる。現代美術が何と格闘しているのかを。
「宗教美術は、その名の通り宗教を原動力に作品を創り出しましたが、アーティストはそこから飛び立ち、『個人』として独立することで近代美術が誕生しました。そこからはキュビズムや印象派、シュールリアリズムなどさまざまな分析的な表現が出てきて、戦後になり現代美術が誕生。近代美術にはない“新しい表現”を追求することにより確立した、と言えるのではないでしょうか。それに果敢にチャレンジするさまざまなアーティストを見て、自分もそこに身を置いてみたいという思いが湧いてきたんです」帰国後、名和氏はすさまじい勢いで作品をつくっていく。
「感覚の場」に接続される体験を
近代美術にはない新たな表現を目ざす現代美術。名和氏は手探りで出口を求めていく。
もともとは少年像などを造形していたが、現代美術に目覚めて以来、「造形する」という彫刻のあり方そのものに疑問を抱くようになる。やがて名和氏は、ある思いに辿りつく。
「私小説的な世界観や、自分の体験、トラウマなど、個人的な思いを発表する“自己表現”として作品をつくる時代がありましたが、それはもう終わりだろうと思いました。インターネット上に個人の思いや感情はあちこちに溢れていて、容易に遭遇できる。そんな時代に、アーティストが個人的な思いを表現することに必要性を感じない。逆に僕は意識的に自分を消していこうと考えたんです」自分を消す。だがそれだけで新しい表現を創り出せるほど単純ではない。名和氏はもう1段階自分の意識をある場所へ連れていく。

東京都現代美術館 ©2011 Kohei Nawa
「芸術作品を見たときに、『これいいよね』『独特なムードだよね』と、言葉でうまく言い表せないけど確実に何かを感じ取り、それを共有できるときがあります。僕はそれを“感覚の場”と表現し、自分が自分以外の人たちと感覚の場で接続されてつながっていく、そんな作品をつくっていきたいと思いました」
名和氏は、感覚の場に接続され人が何かを感じることを「体験」と呼び、「体験」を起こすものであれば、物質も液体でも気体でもなんでもいいのではないか、という思いに至る。そして、「Cell(セル)」という概念にたどり着き、そこからのちに“名和ワールド”とも称される作品を続々生み出していくのだ。
飽くなき探求
「自分の感情が入り込む余地のない単位にまで自分を解体すること」を目ざしてたどり着いた概念「セル」。「細胞、小部屋」などの意味があるが、世界を構成する最小単位であり、その組み合わせによって世界ができていく、という思いも込められている。この概念から、表面をガラスビーズで覆ったシカの剥製の『BEADS(ビーズ)』、モチーフを虚像にしてセルの中に閉じ込めた『PRISM(プリズム)』などいくつかのシリーズに発展していく。
名和作品には、シリコーンオイル、発泡スチロール、発泡ウレタンなどの素材が使われている。また『Dot-Movie(ドット・ムービー)』という映像を使った作品、発光させた無色透明のシリコーンオイルに泡を発生させる『LIQUID(リキッド)』など、旧来の「造形する」という彫刻の概念からは、かけ離れた作品も数多く存在する。
そして『シンセシス』展で新たな作品を加えるにあたり、名和氏はさらに斬新な表現方法を思いつく。「3Dデータを彫刻する」という試みだ。

「現代に生きる人間にとっての脅威(モンスターのような存在)を表現した」という『MANIFOLD(マニホールド)』という作品は、当初、油粘土を使って試作品をつくっていた。ところが、名和氏は「このやり方は古い」と感じてしまう。そこでペン型の触感デバイスを使用し、画面の中のデータであるにも関わらず、実際に触れているかのような感覚で造形する3Dモデリングにチャレンジする。そして模型の実体化には3Dプリンターを選択。これはデジタル作品を評してよく言われる、血の通っていない作品などというものではなく、アナログである自分のフィジカルな感覚をも盛り込める新しい手法と言えるだろう。「学校で教わる彫刻は、つくり方や素材に一定のやり方があります。でも、世の中にはもっといろいろなものが溢れている。自分の表現したい内容に合わせて、その都度自分にフィットした方法、素材を選んでもいいと思っています」
『シンセシス』展は、開催されるとともに人気を呼び、休日には入場制限が行われるほどの来場者を集めた。多くの人たちが、確実に自分以外の何かとつながり、何かを「体験」できる彼の作品に、次々と魅せられているに違いない。
名和晃平氏と3Dプリンター
名和氏は2009年ごろから、スタディとして3Dプリンターを使用。当初はキャベツをスキャンし、3Dプリンターで造形していた。『MANIFOLD』は2012年9月に韓国で設置予定の彫刻で、本来は高さ13m×幅15m×奥行12mと巨大だが、『シンセシス』展では30分の1のモデルと、180近くの実寸パーツのうち33パーツが展示された。33のパーツは5軸制御のNC加工機を使って発泡スチロールで作成することに。そして30分の1のモデルの制作に選ばれたのが、3Dプリンター『Dimension(ディメンジョン)』だった。

「光の当たり方や、下から眺めたときの印象などは物体にしないと最終的な検討ができない。その意味でも、3Dプリンターによる出力は欠かせないと考えました」名和氏は、彫刻の将来をこう予測する。
「グラフィックデザインの世界では、1980年代から2000年くらいの間に、完全にデジタルに移行し、いまやアウトプットはプリンタを通すのが当たり前です。3Dの世界でも確実にデジタル化は進行していくと思う。スキャンしたデータにエフェクトを加えたり、アルゴリズムを使った幾何学的な造形物など、建築物などにもよく見られるようになりましたが、これからは従来のものとまったく違う発想の彫刻が生まれてくると思います」