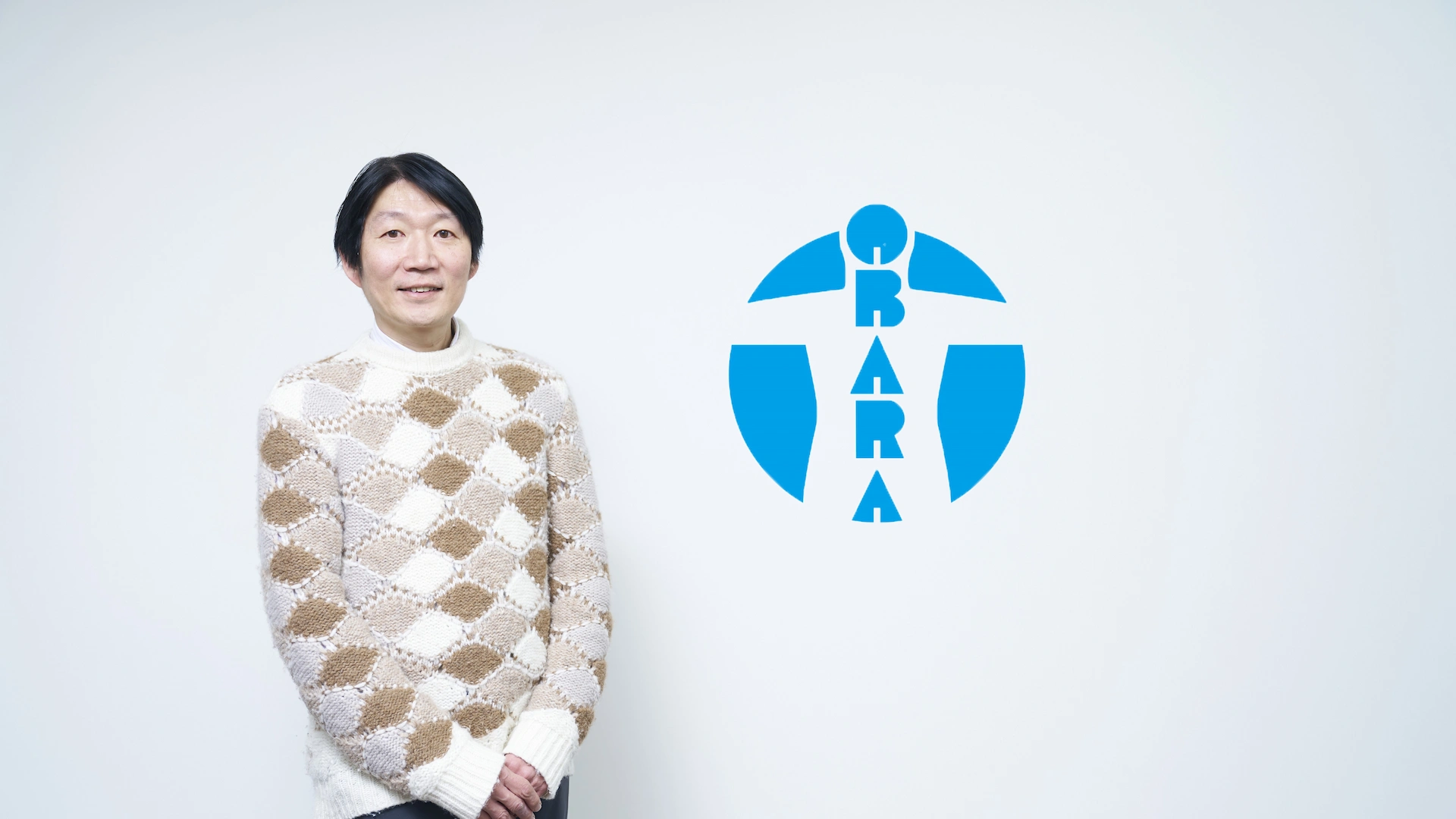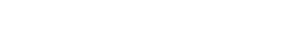2024年4月に、三菱電機株式会社の自動車機器事業が分社化する形で発足した三菱電機モビリティ株式会社(以下、三菱電機モビリティ)。主に自動車機器分野を専門として、電動化部品や先進運転支援システム(ADAS)、環境対応機器などのさまざまな製品や部品の開発・製造を行っている。
部品などの量産に必要となる金型についても、設計から製造までワンストップで取り扱っているが、納期遅れを防ぐための工程管理(スケジュール管理)や、ボトルネックの発生を防ぐための作業負荷の平準化などは属人的な対処に頼る部分が多く、システムによる自動化が喫緊の課題となっていた。
三菱電機モビリティ 技術統括ユニット 高度技術ソリューション部で、ProLeiSによる工程管理の自動化や、各工程の作業負荷の平準化(山崩し)に取り組んだ、同部工具第一課 課長 仲矢智之氏、同課 上田正志氏、同課 加工係 池田秀作氏の3名に話を聞いた。
- 金型製造に関する工程管理を自動化したい
- 金型製造における各工程の作業負荷を平準化したい
■ProLeiS導入の背景
1.多種多様な自動車関連部品などの金型を製造
三菱電機モビリティでは、自動車関連のさまざまな製品や部品の製造を行っている。自動車を構成する電動化部品をはじめ、先進運転支援システム(ADAS)やエンジン制御・車両制御に関連した部品や製品など、取り扱い品目は幅広い。
その中で、工具第一課では樹脂の成形部品などの製造に関連する業務を担当しており、製造に必要となる金型についても、その設計から製造までを一貫して担っている。特にエンジン制御系の部品を多く扱っており、EGRバルブ(排出ガス再循環制御弁)やパージコントロールソレノイドバルブなどに使用する成形部品用金型を製造している。
2.金型製造に関する工程管理と各工程の作業負荷の平準化が重要課題
そうした部品の成形品製造には金型が必要になるが、多種多様な金型の設計から製造まで工具第一課が担っているため、生産管理システムなどを活用した金型製造の工程管理や、各工程の作業負荷の平準化は重要なテーマであったという。
「以前に使用していたシステムには自動化の機能がなく、工程管理は完全に人に頼っていたため、担当している管理者の判断に委ねていました。そのため、現状の工程に新たな仕事を入れなければならない際に、他の金型の納期を遅延させることなく受け入れが可能かの判断も、すべて属人化していました」と仲矢氏が問題点を指摘する。

その解決には、システムによる工程管理の自動化が重要なテーマだった。納期遅れを発生させることなく、工程全体での作業効率を向上させるためには、いわゆる山崩し(作業負荷の平準化)も重要な課題となり、そうした機能をもつ金型製造のための生産管理システムへのリプレイスが検討されることになった。
■ProLeiSの選定理由
3.多くのソリューションを検討し、最終候補を2つに絞り込み
「従来使用していたシステムは、Windows11での動作保証がなく、それに代わるシステムの検討をある時期から始めていました。関連ソリューションを扱う展示会などに積極的に出向き情報収集しました。検討の結果、ProLeiSと、もう1社のソリューションの2つに絞り込み、双方にデモをしていただきました」と池田氏。
4.標準機能で課題を解決できるProLeiSを選定
2つのソリューションのデモを比較し、詳細を確認した結果、三菱電機モビリティは、ProLeiSの採用を決定した。
「ProLeiSのデモを見て、見た目にも新鮮な感じがしたことに加えて、システムとしての発展性、拡張性の高さに、とても魅力を感じました。もちろん、工程管理や作業負荷の平準化についても、ProLeiSは自動化できますし、当方の希望を満たしていました」と池田氏は、選定理由のひとつに将来的な拡張性もあったと話してくれた。

もう一方のソリューションは自動化が弱く、手作業での設定が必要な部分が多々あり、作業負荷の平準化は手動の操作が必要になり、また自社の環境に適合させるためにはシステムのカスタマイズが必要だった。三菱電機モビリティが求める機能を実現するには、標準機能として必要な機能を実装しているProLeiSが適していたという。
またProLeiSはクライアント数が十分に用意されているため、現場の作業員や管理者の一人一人がシステムを活用できる運用環境を容易に構築できるが、他社のソリューションは使用者数に応じてライセンス費用がかかるため、限られた導入費用の中で使用者数が制限された運用形態になってしまう問題があった。
■ProLeiSの導入プロセスと導入効果
5.導入決定から実稼働までのプロセス
ProLeiSの導入決定後、2024年3月にシステムサーバーを導入して立上げ作業に入り、同年10月に本格稼働に至った。
本格稼働に至るまで、多少の不安もあったという。
「ProLeiSは海外メーカーの製品のため、信頼のおける販売店経由でないと、後々のトラブルが心配でした。その点においては、丸紅情報システムズ(以下、MSYS)が間に入ってサポートしてくれるということでしたので、MSYSを信頼して導入立ち上げを開始しました」と池田氏はいう。
問題のひとつは、ProLeiSの開発元であるTebis社とのコミュニケーションにあったという。
「基本的には、MSYSを経由したコミュニケーションになっていたので、こちらの意向や確認事項が正確に伝わっているのか気になることもありました。日本の企業としては、当社が最初の導入ということもあり、マニュアルや手順書といったドキュメントは、すべて日本語に翻訳したものを提供してもらいましたが、部分的に確認が必要な箇所もあり、都度MSYSに問合せをし、定例のミーティングを逐次行うことによって、確認を進めることができました」と池田氏は当時を振り返る。
また、業務上使っている専門用語・業界用語の認識について、「言葉だけでいうとなんとなく伝わるのですが、我々とTebis社で、微妙に言葉のニュアンスが違っているために、立ち上げ当初は、その認識合わせに時間がかかることがありました。中には業界特有、当社特有の使い方などもありました。一緒に立ち上げ作業を進めるにつれ、こうした問題は気にならなくなりました」と上田氏。
6.ProLeiSの導入効果
ProLeiS導入にあたっては、解決すべき課題を三菱電機モビリティとMSYSのタッグにより順次解消していき、現在の本格稼働に至っている。
その導入効果について、上田氏は次のように話してくれた。
「実感として、工程管理と工程の作業負荷の平準化という課題に対して、効果が出てきていると思っています。本格稼働してまだ数カ月しか経過していないこともあり、操作に少々不慣れなところはあります。ただ、そうした問題は使っていくうちに解消されていくものと考えています。最も解決したかった課題のひとつである山崩しについては、当初のイメージ通りできている印象です。

現在、作業負荷の平準化はできていますが、今後、繁忙期において、平準化した上でもなお納期遅れが発生しそうな状態の時に、ProLeiSのシミュレーション機能によって対応する準備を進めておきたいと考えています」と上田氏はさらなる活用に目を向けている。
ProLeiSの今後の活用や、MSYSへ期待すること
7.ProLeiSの今後の活用について
ProLeiSには、工程管理を自動化する機能以外にも、金型製造を効率化するための多様な機能が備わっている。三菱電機モビリティでは、現状、工程管理や工程の作業負荷の平準化での活用が中心になっているが、今後はさらに活用の幅を広げたいという。
「現在は、金型製造の現場での活用にとどまっていますが、その前後の工程の効率化についても、ProLeiSを活用したいと考えています。例えば、製造の前段階である設計フェーズや、金型製造後の出荷前作業やコスト管理などについても活用していきたいと考えています。また、現場の切削加工工程の作業が完了したら、その作業完了を知らせる信号が加工機から発せられて、実績稼働時間を自動で記録し、仕掛中のものがあれば、それについても把握できるようにするなど、より緻密な実績管理ができるようになれば、さらに計画の精度も高められると考えています。もっといえば、協力会社に委託している分についても、ProLeiSを使って、内製分と合わせて一元管理したいと思っています。現在は、協力会社への委託分は別管理であり二元管理・三元管理になっていますが、ProLeiSを活用すれば、その部分も効率化できると考えています」と仲矢氏は、さらなるProLeiSの活用に意欲的だ。
8.MSYSへ期待すること
充実した機能を備え、発展性、拡張性にも優れたProLeiSは、金型製造向け生産管理システムとしては、極めて活用価値の高いソリューションだといえる。

池田氏は、この点について次のように話す。
「将来的にProLeiSユーザが増えていけば、他のProLeiSユーザと情報共有することができ、より良い使い方を学べたり、こちらが気付かなかった使い方を相互に教えてもらえたりと、多くのメリットを享受できるのではないかと思っています。また、他社がメーカーにリクエストした機能が実装されることによって、自社の運用の高度化にも期待しています。ぜひ日本国内の金型製造メーカーにもProLeiSによる実用的な機能性を体感してもらいたいと思います」